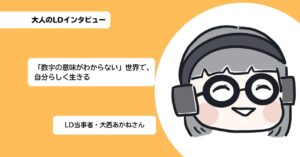”数字は苦手”でも、言葉を力に ― LD当事者・ウェブライター翼祈さんの体験談
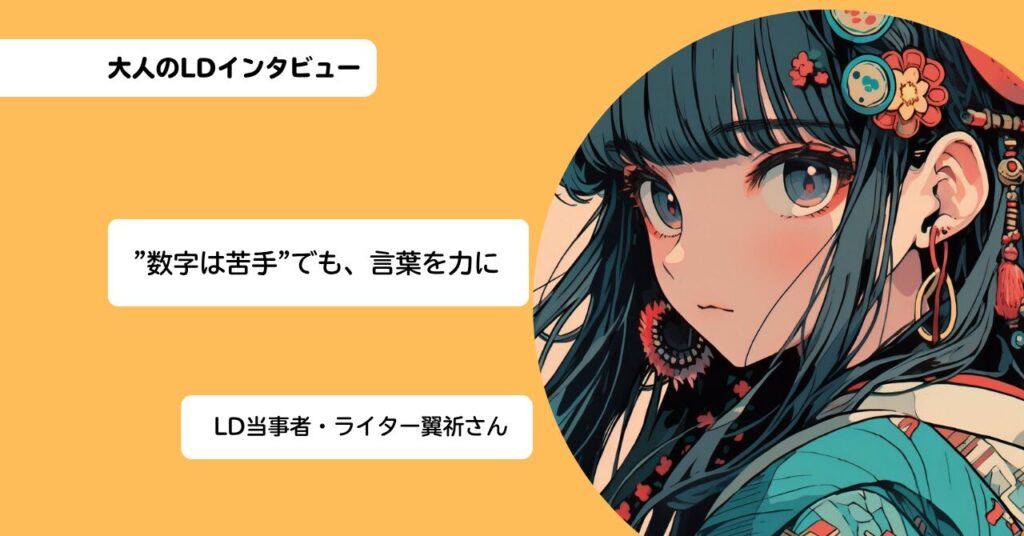
文章の読み書きは問題なくできても、数字や計算に関わることが極端に難しい。そんな算数障害(ディスカリキュリア)の特性を抱えながら、ウェブライターとして活躍する翼祈(たすき)さん。学生時代に数学が理解できず苦しんだ日々、そして「できない」と言われ続けた職場での経験を乗り越え、ウェブライターとして自分の強みを見つけ、いま楽しく働けるようになるまでの歩みを伺いました。
「勉強しないからできない」と思われてきた学生時代
翼祈さん:
翼祈(たすき)というライター名でウェブライターをしています。性別は女性で、年齢は30代です。ウェブライターとして就労継続支援A型事業所「TANOSHIKA CREATIVE 諏訪野」で仕事をしています。
おとなLDラボ_Ten:
今回 LDの算数障害の診断がついているということですが、算数障害とはどのような困りごとがあるのでしょうか?
翼祈さん:
私は普通に文章も書けますし、読めるんです。診断を受けた時はLDとしか言われてないので、正式な診断名がついてるわけではないんですが、自分が思い当てはまるところとしては算数障害かなと思っています。
おとなLDラボ_Ten:
診断がついたのはいつ頃ですか?
翼祈さん:
20歳ごろですね。いろいろあって、ちょっと精神を病んでしまったんです。最初の病院では「適応障害」と言われて、でも治療しても症状は良くならなくて。
その後、母の知人の紹介で別の病院に行ったら、「発達障害のLD(学習障害)・注意欠如・多動症(ADHD)・自閉スペクトラム症(ASD)ですよ」といわれ、そこで診断がつきました。
おとなLDラボ_Ten:
算数だけに特化して困りごとがあるということですが、それに気がついたのはいつ頃ですか?
翼祈さん:
学校の授業ですね。特に数学は全くできなかったです。苦手意識が出たのが、中学校入って2回目の試験ぐらい。学年が上がるごとにどんどん内容が難しくなるじゃないですか。その時に数学を全く理解できてなくて。
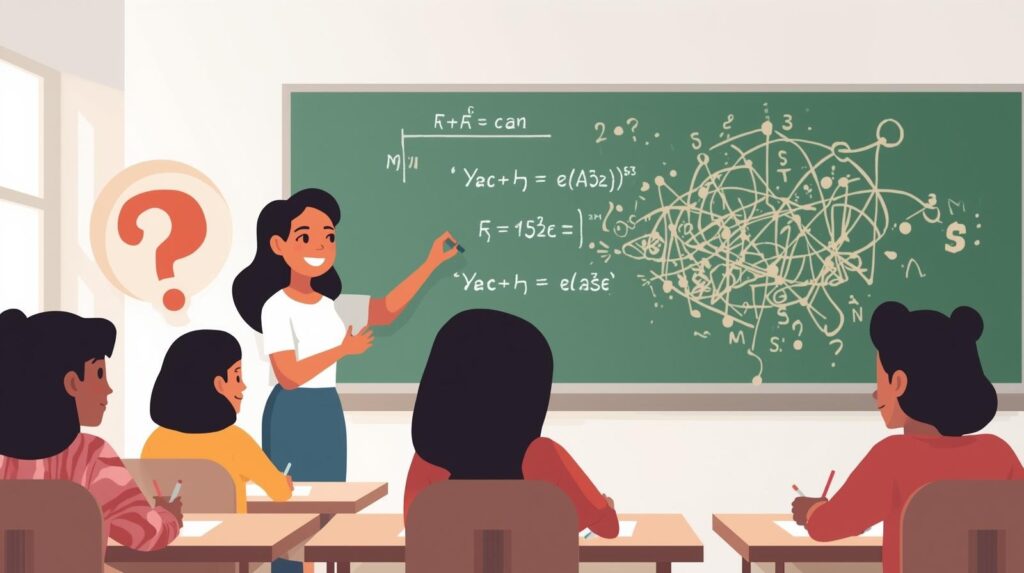
授業もついていけないですし、もともと基礎を理解していないので何を言われているか、全くわからない。グラフも書けなかったですし、とにかく計算が全くできないんですよ。
今でも、計算するために電卓は持っているのですが、電卓で計算しても毎回答えが違うんですよ。それぐらい計算がうまくできない。
特に昔は「勉強ができない=努力してないせいだ」というイメージがあったじゃないですか。「この人は数学の勉強をしてないから、数学ができないんだ」って言われてたぐらいの時代だったんで。テストもひどい点数ばかりでした。
高校に入っても、本当にできなかったですね。私があまりにもひどい点数をとっているから答案用紙を渡す時に、先生が怒りで手を震わせながらグーを握りしめて怒ってたんですよ。その先生を見て逃げながら答案をもらっていくっていうぐらい悪くて。数学だけ成績が悪かったですね。他の教科はできなくてもとりあえず「3」だったりしたんですよ。それが数学だけ…特に高校の先生は厳しかったので、その先生が担当の時には数学は「2」でしたね。それぐらいできなくて。
受験勉強の時も「数学をやらなきゃ」と思って学校に残って先生に聞くんですけど、家に帰ると何を書いてるかわかんない。なので、勉強にすごく困りました。
あと、これがLDのせいなのかはわからないんですが、地図が読めないんです。なので地理もわからないんですよ。地名とかもよく覚えられないですし、道路も含めて地名とかも本当に全くわからない。「車の免許持ってなくてよかったな」って思うぐらい。
例えば「ここは○○という道路だよ」って言われても全く覚えられない。道が覚えられない。さらに、すごい方向音痴なんです。どこかに出かけるときも、前に訪れたところの延長線上なら行けるんですが、今でも全く行ったことない場所はいつも「帰ってこれないだろうな」という心配が常にあるので、基本的に知らない場所には行かないです。
これは算数障害じゃないかもしれないんですけど、この地図が全くわからないというのは学習障害の一つなんじゃないかなと私は思ってます。
おとなLDラボ_Ten:
LDの人って独特の空間認識があるのかもしれませんね。僕も小さい頃に歩いて10分の神社なのに、帰りは2時間かかったことがありました。
翼祈さん:
私もある場所で本当に普通に歩いたら10分で行けるところを、1時間かけて行ったこともありました。やっぱりそういうところはLDなんじゃないかなと思ってます。
診断は受けてないですけど、本当に運動も全くできないので、他にも特性があるんじゃないかと思っています。
あと感覚過敏かどうかわからないですが、私は片耳が難聴なんです。左耳が全く聞こえない。右耳は聞こえるので話せるんですけど、片耳しか聞こえない分、より音を拾おうとするんですよね。結構遠くに離れている人の声とか、もちろん聞こえない部分もあるんですけど、大体何を喋ってるかわかります。
他にも洋服を着るときにタグが痛くて着れなかったりします。試着して買っても帰ってきたら痛くて着れないこともあります。そういうのが自分は診断を受けてないだけで感覚過敏なのかなと思う部分としてありますね。
ただ、空間認識の特性とも関連しているのかもしれませんが、例えば路上で後ろから自転車が近づいてきているのに気がつかなかったり、聞こえるときと聞こえないときがあるなと思います。
おとなLDラボ_Ten:
数学の話に戻りますが、例えば僕も数学がめちゃくちゃ苦手なんですけど、簡単なパターンの計算問題で、公式に数字を当てはめたら解ける問題があるじゃないですか。僕の場合はそれが複雑になってきたり文章題になってくるとダメで…、文章から式を立てることが、難しかったんですよ。
翼祈さんの場合も、数学の中でも「この単元は完全に無理」みたいな境界線はありましたか?

翼祈さん:
ありましたね。小学校の時などに、例えば紙に書いてひたすら割っていったり、掛けていったりという計算問題があるじゃないですか。あれは出来たんです。でも、よくショッピングセンターとかで「○○割引き」とか「○○%オフ」とか書いてある…ああいうのは、もうわからないですよね。もともと抽象的な話や概念が苦手ということもあるかもしれません。
例えば「これ欲しいな」と思って計算しようにも「どうやって計算したら実際の値段がわかるんだろう?」という、そこもわからない。
根本的に数学は全くできない。小学校の時はまだ算数でなんとかなっていたのかなと思いますが、数学になってくると本当にダメでしたね。
得意なことはがんばれる 特性を活かせるライターの仕事
おとなLDラボ_Ten:
数学以外の教科とかはどうでしたか?
翼祈さん:
数学以外の理科も正直あんまり得意ではなかったですね。ただ、記憶力は割と昔から良かったので暗記する教科に関しては結構できてました。
ただそれも、高校になって、できなくなった科目もありました。
例えば、英語は本当に中学校の時はすごくできていて、100点とかも多かったですし、かなり上位だったと思います。でも、高校に入って全くできなくなって。
英語にはリスニングがあるじゃないですか。リスニングって片耳だとすごく不利なんですよ。聞こえづらくて。私が受験する前ぐらいからリスニングが必須科目になったこともあって、どんどん英語の点数が落ちていってしまったんです。他の人がどんどん質問に進んでるのに、私は聞こえづらくて何回も聞き直すので全然問題が進まなくて、成績が落ちてしまって。
最後までよくできたのが日本史でした。日本史は小学校の高学年に初めて習った時から好きで、昔は歴史学者になりたいと思うくらいとにかく好き。日本史は中学校の時から授業で習った内容を教材とかを見ながら、自分だけの暗記用のノートを作ったりして勉強していました。
高校のときにも、そういうノートを作って同級生と一緒に勉強したりしていました。ほぼいつも満点でしたし、日本史だけ偏差値がずば抜けて高い、という感じでした。
おとなLDラボ_Ten:
僕も日本史がすごく好きで小学校の時に歴史漫画をすごくよく読んでたんですよ。ただ小学校の時に歴史で100点取れなかった理由が、グラフや年表が読めなかったんですよね。翼祈さんは、グラフとか年表とかはどうでした?
翼祈さん:
結構覚えられていた方だったと思います。
私は読む方は全く何も問題がなかったですね。記憶力が良かったからかもしれません。
今もウェブライターの仕事をやってて、ネットのニュースとか新聞記事も含めていろいろな記事読んだりするんですよ。
見出しから中身が気になったものを読んでいって、ある程度読んだら内容が理解できるし、次の日に会社に行って上司に「こういうニュースがあったんですよ」って人に話せるぐらい覚えています。
耳も、片耳が聞こえないながらも、耳から覚えることも多くありますね。例えばテレビとか見てて「これ記事の参考になりそうだな」と思ったら、スマホのメモ機能で急いでメモを取って、それを記事の中に入れてたりもします。なので、もともと視覚と聴覚からの記憶が残りやすいんじゃないかなと思います。
そういう理由で日本史に関しては、数学だったら覚えられなかったグラフとか表もカバーできてたのかなと思いますね。
おとなLDラボ_Ten:
なるほど。得意だからこそ読めるという感じですか?
翼祈さん:
そうですね、得意だから読めたと思います。今、私がウェブライターとして働いている会社は、障害・病気・難病当事者による当事者のためのウェブメディアをやっています。私はnoteでも医療系の記事を書きますし、その際に根拠として論文や書籍を引用として使用するために、読んでまとめたりすることもあります。
あるインタビュー記事を作成する際に、難病のお母さんのお話を伺ったことがありました。そのなかでは、どうしてもたくさん医学用語が出てきてしまうんですね。でも同僚から例えば、「この『処置』という言葉は若干難しいから他の言葉はない?」と聞かれて、「『治療を受ける』でもわかりやすいですよね」という提案ができたりしました。
そういう医療用語も、ある程度読めて理解できています。他の人が読めないような漢字、例えば「聾学校(ろうがっこう)」の「聾(ろう)」も読めます。他の人に「この字は難しくて読めない人も多いから、ひらがなに変えたほうがいい」と言われて、初めて自分が難読漢字を読んでいることを知りました。
ウェブメディアの特性上、多くの障害・病気・難病の記事を作っていて、今も新しい治療法治療薬研究の記事を書いていますし、その覚えたことが知識として身についています。
今は仕事で計算をすることがまずないですし、私が持っているASDやADHDの特性はウェブライターという仕事をやるうえで、すごく活かせているなと思います。
特に、記事作成に関しては平均的に毎日3記事は書いていて。自分ではあまり自覚はないのですが、人からは「書くのがすごく早いですね」と言われます。ある時は1万5000字を4時間で書いたこともあります。
私としては、ただ毎日同じことの繰り返しで自分の決めた目標を同じようにただやってるだけなんですが、人によってはものすごい早いって言われます。なので人に言われるまで、自分は当たり前のことをただやってるだけで、早いという自覚もあんまりなかったですね。
おとなLDラボ_Ten:
今、A型事業所で働かれてるということなんですけど、高校卒業して大学へ行ってからA型事業所に行かれたのでしょうか?
翼祈さん:
大学はいろいろあって1年で中退してます。そこから約10年間ぐらい引きこもりをしていました。それで今から約10年前に働こうと思って、10年前の12月から働き始めて、なので働き始めてからまだ10年も経っていません。
最初に働き始めたのもA型事業所で、今の会社は3カ所目です。2025年10月11日で入社して4年です。私の自社メディアの記事は、これから書こうと思ってる記事を含めたら1000本超えますし、noteの方も930記事前後書いてます。今も毎日、40本以上は書いています。
おとなLDラボ_Ten:
それはすごいですね!
翼祈さん:
ずっと書いてますね、本当に。自分が書きたいものを書いてて、「今週は自社メディアの週」とか、「今週はnoteを書く週」とか決めてそれを交互にやっています。
社外の方のインタビュー記事の編集もしてますし、社外の方との先方とのやり取りも
やってたりするんで、(書く以外の)仕事もいろいろやってます。
自社メディアの「AKARI」の公式SNSの更新も担当しているので、朝一に更新しています。会社の広報としてブログも書いてますし、見学者にライター業務の説明とかもたまにしてます。最近は参加してないですけど、広報誌のインタビューに参加して質問を考えたりインタビューしたりすることもあります。
参考
おとなLDラボ_Ten:
ところで、翼祈さんは数字が苦手ということですが、今のお話ししていただいた中にはとてもたくさんの数字の記録の紹介があります。これは記憶力の良さで覚えているということなのでしょうか?
翼祈さん:
そうですね、多分、記憶力でカバーしています。私は記事を探す時に、ある程度読んだら内容を理解し、次の日とか、1ヵ月以上後に上司に話しても、覚えて話しています。
今日は、3ヵ月前に読んだ内容も、話しました。
片耳難聴でも、耳からも情報が残りやすいです。会社で、2年以上前に誰かが話した内容も、その人がこういう言い回しで言ったなど、同じ口調で話すことができます。
話した相手はそれを覚えておらず、「よく覚えていますね」と言われます。
自分が書いた記事はほぼ全部、同僚が書いた記事の内容も、大体覚えていますよ。
おとなLDラボ_Ten:
高い記憶力でカバーされている、、なるほどです!
「なんでこんな障害に」絶望した診断直後 今の事業所で自分の言葉で自分の意思を伝える力が身についた
おとなLDラボ_Ten:
ちなみに学生時代にA型事業所以外に、他の一般企業でのアルバイトなどはされたことはありますか?
翼祈さん:
大学を中退したころに年賀状の仕分けのアルバイトをしたことがあります。あと、少しだけ契約社員として働いたこともありますが、その時はメンタル的にあまり調子が良くなくて、なかなか行けないまま契約が終了してしまいました。
その後、2年間で150件以上面接受けたんですよ。でもほぼ不採用で。そのことですごく病んでしまって、もう体というか頭が持ち上がらなくなってしまって、そこから10年間引きこもりを続けたという感じです。
なので、ほとんど働いた経験はなくて、20代の時にも社会人という経験はしてないです。
おとなLDラボ_Ten:
年賀状の仕分けの仕事をされていた時や契約職員として働いていた時に、算数障害特有の困り事を感じることはありましたか?
翼祈さん:
算数障害はそんなに影響はなかったと思いますけど、例えば住所が覚えられなくて分けられなかったりとか、仕分け用の機械の使い方がわからないということはありました。
契約社員は食品の会社だったので、食べ物がどんどん出来上がってくるんですね。その時に頭と体が追いつかなくなってしまって。だからいつも機械を止めてしまっていましたし、手順にもなかなか追いつけなくて大変でした。
当時、私は障害者という自覚も特になく、障害者雇用という言葉も知らなかったので普通に一般社員として働いてたんです。雇う側も障害のない人として雇ってるので、「こんなのもできないのか」みたいな感じで現場の人ともすごく雰囲気が悪くなってしまいました。本当にできなかったんで。
私が発達障害の診断を受けた時には「発達障害」という言葉もほぼ知られていませんでした。当時はSNSで「県外でもいいのでどなたか専門医のいる都道府県を知りませんか?教えてください」って言ってたぐらい発達障害という言葉がまだ全く浸透してなくて。だから私も当時は「なんで自分は誰もかかってないような障害を負ってしまったんだ」って思うぐらい、とても絶望してたんです。
私は片耳難聴・聴覚障害者というときは普通に話せてたので、障害者扱いはされていませんでした。学校でも、私は左側が聞こえないので右側でよく聞こえるようにテストの時などに左端に座らせてもらうとか、いろいろ配慮を受けてましたけど、周りも自分も、私が障害者だと思っては生きていませんでした。
それが発達障害という診断を受けて…当時は本当に情報がなかったので、「誰もかからないような障害になってしまった」と落ち込みました。本当に発達障害と診断を受ける前と受けた後で、ものすごく生きづらさが変わったなと思いましたね
おとなLDラボ_Ten:
LDは日本では2000年代に広まってきて、僕は今27歳なんですけど、僕ぐらいの年齢で大人になってからLDに気づく人は「どこでどういう診断を受けたらいいのかわからない」という方がすごく多いんですよね。
翼祈さんはLDをどうやって知ったのか、まずそもそもLDという概念をどう知ってどうやって診断を受けたのかを、もしよければ覚えてる範囲で教えていただきたいです。
翼祈さん:
私は診断を受けた時には「LD」という言葉だけしか知らなかったです。何を表すかも全く分かっていませんでした。でもウェブライターになって記事を書くために調べたら、算数障害が自分に当てはまることがすごく多かったんです。
「LDとは聞いてたけど、でも読み書きでも書字でもないと思う。消去法で言えば算数障害じゃないかな」と思って。正式には(診断名としては)言われてないけど、いろいろ自分の昔のことを振り返ってみると、算数障害で間違いないなと思っています。
ASDとADHDも自分の中ではこだわりの強さとか過集中はそうなんだろうなとか思っているんですが、3つも併発してる人はそんなにいないみたいなんですよね。自分の周りでは、例えばLDじゃない他の精神疾患を併発してる人はいても、LDを併発してる人はあまりいないです。
なので私も「LDって結局何なんだろう」って思いながら…、でも診断を受けたのでウェブライターとしてプロフィールを書くときに「自分はLDがあります」と書いてたんですけど、それがよくわかってないままだったんです。でも、実際に自分がLDの記事を書いたことでようやく、腑に落ちたという感じですね。
おとなLDラボ_Ten:
めちゃくちゃ良い体験ですね。診断が下りた後などで、家族など周りの人はどのような反応でしたか?
翼祈さん:
もともと全く計算はできなかったので、両親もLDとか算数障害という概念がなかったとしても、私の小さい頃からの行動を見て「この子は相当算数ができないな」とは思っていたと思います。
日常生活の中でも買い物とかでざっくりとした計算が全くできないので、すごく返品してしまったりとか、レジで「これ返します」とかもすごく多いんですよ。
おとなLDラボ_Ten:
実際に知った後と知る前で比べて、ご自身の状況とか他の人への伝え方に変化はありましたか?
翼祈さん:
特に自分が算数障害の記事を書いてからは、ちゃんと電卓で計算しようという意識を持つようになりましたね。紙に書いて計算しても、桁を間違えたらひどい数字になるので。
今は電卓アプリがスマホに入っているので、電卓で実際に数字を打って計算する。何回かミスはしますけど、ちゃんとした数字を入れたらちゃんとした数字が出てくるので、電卓を使うのは意識してます。
前は闇雲に「この買い物は○○円くらいで済むだろう」と思って計算もせず買ってたんですよ。それが今はちゃんと計算をして、なるべくオーバーしないように買い物するようになったというところはあると思います。
おとなLDラボ_Ten:
事業所だと、ADHDやASDの配慮はしてくれるけどLDの配慮はあまりないという話をたまに聞くのですが、翼祈さんが通われてるA型事業所ではどんな配慮がありますか?
翼祈さん:
会社では、数学というか計算を求められることはまずないですね。ASDやADHDの方はいらっしゃるのですが、LDの方はいないんです。ライターとしては記事を書くことで成果を出せたらしっかり評価される会社なので、今の会社においては配慮してもらわなくてもできてる方なんじゃないかなと思ってます。
ライターの仕事において算数障害って特に不利なことはあまりないかなと感じています。計算ができないという場合でも電卓で出来ますし、パソコンで調べたらすぐに正解が出てくるので。例えば私は数字が弱いので西暦と和暦がわからなくなることもあるんですが、調べたらすぐに出てきますよね。
だからそんなに会社でLDで困ってる話も特にしてないですし、自分自身も仕事しててそんなに困ってることはないです。
おとなLDラボ_Ten:
過去に所属されていた事業所では配慮はあったんですか?
翼祈さん:
1カ所目は単純作業で、2カ所目はものづくりの事業所でした。なので特にLDであることは影響はなかったような気がしますけど…影響があったなと思うのは、単純作業では作業工程が順番通りにできなかったり、ノルマを達成するのが遅かったりということがありました。
ものづくりに関しても、作業工程を理解できなかった。その会社には5年ぐらいいたんですが、一番最初に習ったものを作るだけで終わってしまいました。他の人がいろんなものを作っているのをみて「私もああいうの作れたらいいな」と思ってはいたんですが、でもその実力がなかったですし、覚える力もなかったですね。
本当に1ヶ所目と2ヶ所目の会社の時には「何もできない」とずっと言われてたので、あの当時は「なんで自分はこんなに何もできないんだろう」と思うことも、とても多かったですね。
実際にこうやってお話したり、自分の意見を言えるようになったのも今のA型事業所に行き出してからです。自分の意思を持ったり、自分の言葉で伝える力がついたと思います。それまではずっと人の顔色を伺って、いかに人に悪く言われないかって生きてたんで。
本当に今の会社に入らなければ、こうやってインタビューも受けてないでしょうし自分の言葉で自分の意思を伝えるという力も身についてなかったと思います。
LDもそんなに問題ないので、そういう点では今の会社に入ってよかったなと思っています。他の発達障害の特性も今の会社にはぴったり合っているし、本当にうまくピースがハマって今こうやってウェブライターという仕事を楽しくやれてるんだろうなと思ってます
自分に合ったツールで生きづらさを乗り越えよう
おとなLDラボ_Ten:
電卓をよく使われるということなんですけど、電卓以外にもこんなアプリやサービス、環境があればもっと自分の生活や仕事がより楽になっていくかもとか、自分の困りごとが助かるんじゃないかなと思うツールはありますか?
翼祈さん:
地図ですね。例えばGoogleマップなどの地図アプリが読めないんです。「駅からすぐ」と言われてもどこだかわからない。そういう、地図が読めないLDの人向けの優しい地図のアプリがあれば、私も読めるようになるのかなと思います。
人に聞いてもまず地名が分からないですし、地理も分からないのでたどり着けない。私の母はすごく地図を読むのが上手なので、母に聞いて指示をもらってから行くようにしています。自分一人では行けないです。
それで諦めることも多いので、LDがあっても行きたい場所に行けるような地図アプリがあったらいいなと思ってます。
おとなLDラボ_Ten:
翼祈さんの周りには同じような当事者の方はいらっしゃいますか?当事者同士のつながりを増やしていきたいと思うことはありますか?
翼祈さん:
LDに関しては私自身も今まで当事者の人に会ったことはないですし、相談したこともないのでそもそも「周りにいたらいい」という考え方をあまり持ったことがないかもしれません。
どう相談していいかわからないっていうのが本音かもしれないです。
自分の他の障害とか病気とかに関しては、片耳難聴の交流会に参加したことあるんですけど、「本当に片耳難聴の人って他にもいたんだ」って思うぐらいで。でもそれを耳鼻科の先生に話すと「普通にいますよ。よく来ますよ」って言われて、実は身近にいるんだなって思いました。
先生たちにとっては当たり前でも、その人たちを目の前にするまではわからなかったので、(LDの人に関しても)近くにいても気づけないというのもあるかもしれませんね。
おとなLDラボ_Ten:
それでは最後に、同じ悩みを持ってる人や算数障害の悩みを持ってる人に向けて一言お願いできますか。
翼祈さん:
発達障害は先天的なもので脳に障害があるといわれていて、これは「努力したら解決する」とか「努力したらできる」っていうものではありません。生まれつきなものなので、自分だけで解決しようとするのは、まず難しいと思います。

でも今は、いろんなLDを助ける教材もありますし、「LD」という言葉が広がってきて、LDを支援する団体も増えてきています。私も昔、数学ができなくて困ったなと思っていました。でも今、それなりにこうやって大人になってウェブライターという仕事に就いているので、確かに計算ができないっていうことは非常に困りますけど、カバーできるツールも増えてます。
仮にLDとか算数障害だという診断を受けても、いろんなものを利用することでその人たちの生きづらさが解消されたりLDとか算数障害を持ってても生きやすくなるような体制が今ちょっとずつ整ってきていると思います。
なので発達障害と診断を受けたとしても落ち込まずに、利用できるところは利用してその人が生活しやすいように暮らせていけたらすごくいいんじゃないかなって思います。
私自身も、使えるアプリとかツールに関してはこれからも使って自分の生活に困らないように生活していきたいなと思っています。
本記事は、朝日新聞厚生文化事業団による「『発達障がい』とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025」を受けて実施したインタビューをもとに作成しました。