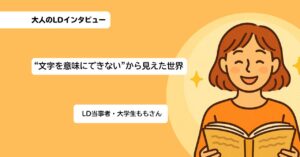「数字の意味がわからない」世界で、自分らしく生きる―算数障害当事者・大西あかねさんの体験談
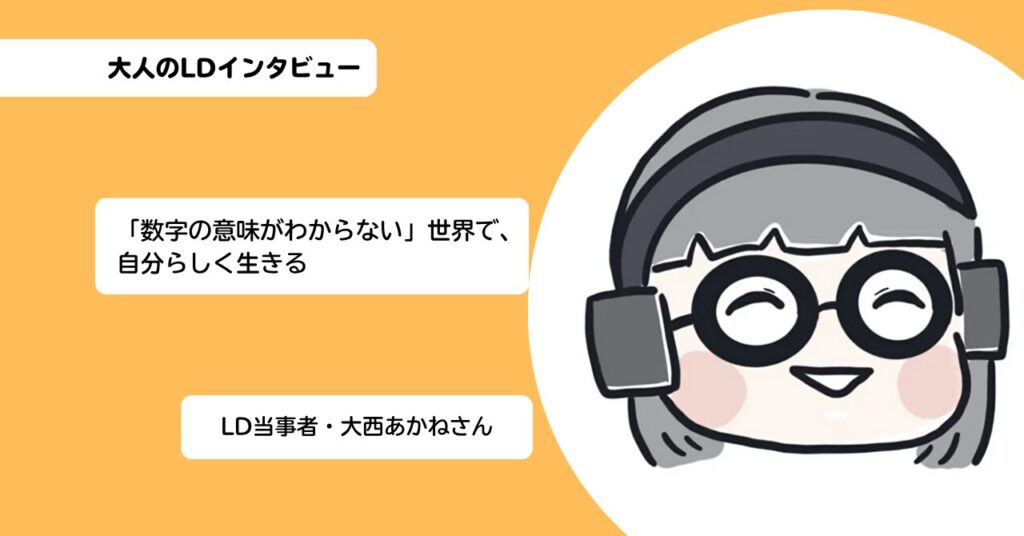
幼い頃から数字の概念が理解できず、算数の時間が苦痛だったという大西あかねさん。20歳で「算数障害」と診断を受けてから、自分の特性をどう受け止め、どう伝えていくかを模索してきました。今ではその経験を社会に発信し、同じ悩みを抱える人たちに勇気を届けています。そんな大西あかねさんに、これまでの歩みについてお伺いしました。
「0」、「1」、「2」の意味が分からない 算数障害とは
あかねさん:
大西あかねと申します。年齢は29歳で、埼玉県に住んでいます。主婦をしながら、Ledesoneでも算数障害の啓発に関わっています。
高校時代からナレーターや舞台、ラジオのパーソナリティとか、ニコ生などのお仕事をしていました。
おとなLDラボ_Ten:
あかねさんご自身がLDだと診断、もしくは認識されたきっかけは?
あかねさん:
私が診断を受けたのは20歳の頃です。最初はADHDで悩んでいて…「不注意多いな」とか「忘れ物が人より多いな」とか「なんでできないんだろう」みたいなことが多かったんです。でも、当時から数字も難しくて。小学生のときからずっとできなくて、算数もわかんないし…みたいな感じで当時の友人(現在の夫)に相談したら「検査を受けてみたら?」ということで、「じゃあ、受けてみようかな」って軽い気持ちで検査を受け、診断がおりたのが20歳の時ですね。
おとなLDラボ_Ten:
数字が難しいというのは算数障害の特性として、具体的にどういった困りごとが普段あるんでしょうか?
あかねさん:
私、かなり重めのタイプでして、そもそも(数字の)概念自体が理解できてないんですね。0とか1とか2の意味がよく分かってない。
よくある「1キロが何メートルです」とかもよく分かんないんです。「あと1キロです」ってナビに表示されても、それが理解ができなくて。「あとどれぐらいだろう?」みたいな感じなんですよね。そういう概念自体のことが理解できない分、わからないことが多いかもしれないですね。
おとなLDラボ_Ten:
例えば「○年先」とかがわかんなかったり、時計とかも読みにくいこともあるんですか?
あかねさん:
時間は、私はどちらかというと24時間制の方がわかりやすいんです。人によっては12時間制の方がわかりやすかったりとか、それぞれあると思うんですけど、私は12時間制だと午前・午後がよくわからないんです。
午後1時と13時が紐付けられないので「で、何時?」みたいな感じになっちゃうので、そういう部分も苦手です。
おとなLDラボ_Ten:
続いて、幼少期のお話をお聞きしたいと思います。小学校の頃とか学校生活とかでは、どんな困りごとがありましたか?
あかねさん:
まず小学校1年生の時から、なかなか算数の授業についていけなくて。授業は「先生、何言ってんだろう…」からまず始まる。
私の小学校では、2年生から6年生まで「習熟度別クラス」があったんです。普通級なんですけど、算数の時間だけ、できる子とできない子に分けられる。できない子を30人選抜してクラスをわけて授業を行うことがありました。
そこから6年生まで5年間ずっとその習熟度クラスの「できないクラス」30人の一番上になっちゃって。「できないトップランカー」みたいな(笑)。ずっとその中で算数はやってきていました。
おとなLDラボ_Ten:
習熟度別クラスってあまり一般的ではないかなと思いますが、幼稚園のときの段階から数字の困難さがあって、習熟度別クラスがある学校を選んだのですか?
あかねさん:
いいえ、もともと住んでいる地域の小学校がそういう学校でした。普通に上がっていって、2年生から「習熟度別になるらしいよ」という話があり、5年間ずっと同じ先生が教えてくれました。
算数と理科専門の先生が、算数の時間だけずっと付きっきりで教えてくれたって感じです。
なんで私だけこんなにできないんだろう?ダメだと感じ続けた学生時代
おとなLDラボ_Ten:
その中で勉強での困り事や、先ほどそもそも根底の概念から理解が難しかったっていうお話があったと思うんですが、宿題や学びでの困り事はありましたか?また逆に、「こういう部分を配慮してもらって助かった」ということは?
あかねさん:
私は、診断を受けたのが20歳の頃で、それまでは自分が算数障害だっていうこと自体わかってなかったんです。計算ドリルとか夏休みの宿題とかすごい大量に出るじゃないですか。他の、読書感想文とか貯金箱を作ったりとかはできるんだけど なぜか算数のドリルの提出だけすっごく大変でしたね。
もうずっとやっても終わらないから、答えを見ながらやるみたいな(笑)、「先生ごめんなさい」って。
そもそも宿題が苦手でしたね。漢字ドリルと計算ドリルって宿題でよく出るじゃないですか。でもわかんないので、答えを見て…本当はダメなんですけど、書き写してなんとか提出するみたいな感じでした。
その当時「バトル鉛筆」っていうのがあったんですよ。今もあるかな?テストの時は、そのバトル鉛筆をコロコロ転がして答えていました。もう、あてずっぽうで。でもそれで当たっちゃう時があるんですよ!当たった時に「説明してください」って言われても説明できない(笑)。さすがに「勘です」とは言えないじゃないですか。「なんとなく…」みたいに濁して先生に伝えないといけなかったのが結構つらかったですね。何年か後に、先生に「実は…」って話したときに「知ってたよ。バトル鉛筆」って言われて(笑) 先生にはバレていたみたいです。
そもそも出来るレベルが他人と違ってたということを後から聞きました。
おとなLDラボ_Ten:
その時点では先生から「何か障害があるかも」という話はなかったんですか?
あかねさん:
なかったですね。当時はそこまで算数障害という言葉も知られてなかったですし、普及していなかったと思います。
学習障害って、読みと書きのイメージがついている時代だったので、算数が学習障害の一部としては認識されていなかったと思います。
おとなLDラボ_Ten:
そうですよね。なかなか算数障害って知られてないから気づきにくい、周囲からも気づかれにくいという面が、今もあると思います。
ご両親やご家族で、特性に関しての対応やサポートなどはありましたか?
あかねさん:
父と母と、真逆の反応だったんですよ。父は算数ができる人で「なんでできないんだ」みたいな感じがありました。進研ゼミやったり公文やったり、いろいろやってたんですがうまくいかなくて、結構それで怒られたこともあります。
母は私の特性を知ってたみたいで、「電卓でやってみる?」って言ってくれたこともありました。ただ、小学生の頃は電卓の打ち方が分からなくて。小学生の時は本当に辛かったのですが、中学生でやっと電卓の使い方を知りました。
おとなLDラボ_Ten:
電卓が使いにくいのは、機能的な面で使いにくいのか、算数障害的な困りごとの面で使い方を覚えるのに難さがあったのか、どちらかわかりますか?
あかねさん:
そもそも数字の配列というか、数字の並び方を覚えるまでがすごく大変でした。小学生の時に習う「+(足し算)」「-(引き算)」「x(掛け算)」「÷(割り算)」はわかる。でも他のボタンは謎で・・・教わってもよくわからなかったんです。中学生になってやっと「あ!これは前に習ったこれか」と理解できて。
おとなLDラボ_Ten:
中学の頃はいかがでしたか?
あかねさん:
1年生の4月で、内容につまずいてしまって。あと、それとはあまり関係ないですけど、いじめとかいろんな理由があって不登校になったりしてしまっていたので、暗黒時代でした。
その後、いろいろあってフリースクールに通うことになり、100マス計算をやる機会がありました。もちろん全然できなくて、1時間以上かかっちゃって。もっと長い時もあるんですけど…。「普通の子はもっと早いのに、なんで私だけこんなにできないの?」って思っていました。
システムがわからないのもあるし、計算が暗算でパッとできない。100マス計算やる時って電卓は使えないじゃないですか。やっと覚えた電卓を使えないのでやっぱりわかんない。ダメだなと感じることが結構多かったです。
算数なくても生きていける!信頼できる人との出会いで成長できた
おとなLDラボ_Ten:
フリースクールでは、それまでの学校よりも楽になったという実感はありましたか?
あかねさん:
楽にはなりました。「算数より国語を伸ばした方がいい」と言ってもらえたりとか、大学生のお兄さんお姉さんとの交流がかなり自分の中では記憶に残っています。
算数が苦手なこともちょこちょこ相談はしていました。ボランティアの大学生のお兄さんお姉さんとかに言われたのは、やっぱり小学生の習熟度別の先生と言ってたことと同じようなことで。「算数なくても生きていける!」とか…自分にとって嬉しい言葉をかけてもらっていました。
やっぱり小学生の時から算数ができなさすぎて落ち込んでたりしてたんですよ。算数の時間だけ憂鬱・・・みたいな。テストも、「ドラえもん」の「のび太くん」レベルで、0点とか5点とか叩き出していました。 本当に他の教科と全然違っていました。他の教科は普通の点数をとれるのに、なんで算数だけ?という感じで。
算数だけついていけないから、すごく落ち込んじゃったりしたことがあったので、そういう時に気軽に相談できる相手がいたのは大きかったかもしれない。小学校の時もフリースクールの時もそういう相談できる人がいたのは自分の中では、すごくありがたかったですね。
おとなLDラボ_Ten:
単に「相談する」というだけでもLDとして、言語化や説明って結構難しい部分があるなと思うんですが、あかねさんはご自身の特性、算数ができないという部分を、学校の先生や大学生のボランティアの方にどういうふうに説明してましたか?
あかねさん:
私は、そういう特性などを話すときに冗談混じりで話すことが多いんですよ。相手には重く受け止めすぎてほしくないと思っていて、確かに深刻な状況ではあるんだけれども、それでその相手の人に気を使わせたくないっていう気持ちが、今でもあったりします。
特に当時はその思いがすごく強くて「いや~、のび太くんレベルなんですよね~成績~」みたいな感じの雑談から入っていました。「実は、九九の7の段、8の段とかが、ちょっとわかんないんですよね〜」みたいな、重すぎない相談にしつつ話す方法は、当時もやってた気がします。
おとなLDラボ_中井:
僕もこれよくやっていますね。僕にとってそれは大人の人を試す的な意味もあったんです。相手を試して、それをちゃんと受け止めてくれるか確認したいという気持ちが僕的にはあったんですけど、あかねさん的にもそういう気持ちはありましたか?それともやはり相手を傷つけたくないという気持ちが大きかったですか?
あかねさん:
どちらかというと後者ですね。自分でも算数障害だということを知らなかったので、その「できなさ」の原因にたどり着けない状態で、自分の中でも手探りだった。
あまり試すとかではなく、相手の反応を純粋に知りたいと思っていましたが、でもやっぱり相手に気を使わせたくないという思いが強かったですね。
おとなLDラボ_Ten:
先ほど小学校時代の気軽な相談相手は先生だったという話がありましたが、他には誰かいらっしゃったりしましたか?
あかねさん:
さっきお話しした習熟度別の算数の担当の先生以外は相談できてないです。その先生だけにしか小学の時は相談できていませんでした。中学校の時はフリースクールの大学生のボランティアの複数名の方に相談していました。
おとなLDラボ_Ten:
周りの同級生や友人とかはどうでしたか?
あかねさん:
実はぼっちだったので相談できなかったというのと、相談してもわかってもらえないんじゃないかという思いもありました。
原因も分からないし、なんでできないんだろうっていう理由すら自分でもわからない、情報もない状態だったので。同級生とかに聞くのも…と思っていました。
おとなLDラボ_Ten:
中学校時代と小学校との大きな違いは、やはりフリースクールに入られて大学生の皆さんに特性を説明できるようになったりとか相談ができるようになったことかなと思いますが、先生方は発達障害に関する知識はあまりなかったのでしょうか?
あかねさん
その当時はまだあまり普及していなかったのか、カウンセラーさんとかも発達障害について話されることはなかったですね。
自分がやりたいこととの出会い 悩みまくった学生時代
おとなLDラボ_Ten:
中学校は高校入試とかもあるし、キャリア選択を初めてする機会もあるのかなと思いますが、「算数ができない」部分において、高校進学はどういう風に捉えられてましたか?
あかねさん:
私はずっと自分の声にコンプレックスがあったんです。ある時、専門家の方にお話しさせていただく機会があったので、その話をしたら、「その声は武器になるよ!」っておっしゃってくださったんです。
それで、そういうことが学べる学校に行きたいと思うようになりました。そしたら、地元の中学校の校長先生とお会いできる機会があり、その校長先生に直接進路相談する機会をいただけたんです。その時、「実はこういうことが学べる高校に進みたいと思ってるんです」って話してたら「全然いけると思う!推薦できます」「他の先生が何と言っても、あなたならいけます」、って言ってくれて。小論文や面接などの試験を受けて推薦で合格しました。
おとなLDラボ_Ten:
それは、すごく素敵な出会いですね。
自分の本当にやりたいことに出会って、校長先生もそれを後押してくださるというのがめちゃくちゃ素敵だなと思ったんですが、高校から専門性の高い高校で、一般とは違う道に進まれるということは、親御さんから心配されたりとかはありましたか?
あかねさん:
やっぱり当初は「大丈夫か?」って声はあったんですよ。でもどうしても私は行きたくて。ワークショップや説明会なども何度も行ったりしていて、そんな自分の熱意を見ていた親が納得してくれて、という感じでした。
おとなLDラボ_Ten:
高校でも数学の授業はありましたか?
あかねさん:
高校でも午前中は普通の教科を学んでいました。午後は選択でいろいろなコースごとの授業がありました。
その中でもやっぱり数学だけは本当にできなくて。高校も国語と英語と数学が習熟度別のクラスがあったんですが、やっぱり数学だけがダメだったんですよ。
国語が一番いいクラスで、英語が真ん中ぐらい。数学が全然できないクラスだったんです。3年間それだったので、先生もさすがに分かってるんでしょうね。ちゃんと前のほうの席でちゃんとノート書いて写してるのに全然できてない。だから学習に取り組む態度で評価していただいたりしました。それでなんとか挽回して留年は回避しました。もう本当にギリギリで。
先生もなんとかしようと、暗記問題を出してくれることもあって、「これを覚えてくれば、赤点は回避できる」という問題を出してくれて、必死で覚えて…というかんじでしたね。
おとなLDラボ_Ten:
高校に入って、人間関係や心境に変化はありましたか?
あかねさん:
専門的なことを学ぶ学校だったので、その分仕事に対する熱を感じました。お仕事をさせていただく中で、現場で仕事をしている大人の方々と交流が増えて、お話しさせていただく機会がかなり多くなり、すごく視野が広がった気がします。
ただ、数字が読めないことに関しては、やっぱり同業だとしても隠さないとまずいと思っていたので、数字の困り感については先生方に「内緒にしといてくれ」とは言ってました。
同級生たちに弱みは見せたくないと思っていて、先生たちに「ここだけの話に留めておいてください」みたいな話はしてました。
おとなLDラボ_Ten:
卒業後にどんな職種につきたいという希望はありましたか?
あかねさん:
センター試験は絶対難しいと思っていたので、大学という選択肢はなかったです。ただ、高卒だと就職も厳しいだろうなと思ったので、どこか専門学校へ進学しなくてはと思って。でもなぜかそこで情報系の専門学校を選んでしまったんです(笑)何やってるんだって今なら思えるんですけど、当時はパソコンを扱うのが好きだったので、そういうことが学べる専門学校に入学しました。
おとなLDラボ_Ten:
専門学校に行かれてどうでしたか?
あかねさん:
やっぱり人間関係がかなり難しかったです。戸惑いもありましたし、高校の3年間が特殊な環境だったので、「あれ?どうやって生活するんだろう」って感じました。特に、グループワークとかがうまくできなくて。
親に承諾を得て、資格だけとって辞めました。ちょうどそのときに、企業からスカウトが来たので、そこで働きだしたというかたちになります。
「算数障害?なにそれ?」受け止めきれなかった日々
おとなLDラボ_Ten:
実際に働かれて、仕事上での困りごとなどはありましたか?
あかねさん:
まず、すごくブラックな会社だったんですよ(笑)。朝帰りとか当たり前で、とにかく怒涛の生活でした。エナジードリンクを飲みすぎて、左手が震えるようになってしまったり、完全にメンタルを病んでしまって。そのまま退職しました。
おとなLDラボ_Ten:
仕事をやっていく上で、どうしても数というのは関わってくるのかなと思うんですが、自分の特性や困りごとについては、周囲の人にどう伝えていましたか?
あかねさん:
実は、25歳までは伝えていませんでした。当時はまだ、算数障害があることも知らなかったということもありますが、伝えたらそれが「弱み」と受け取られるんじゃないかという、恐怖心の方が勝ってしまって。隠して生きていましたね。そういう意味では、幼少期のほうが他人に頼れていたかなと思います。
メンタルを病んでしまったときに、適応障害もあるけど、発達障害の相談もしてたんです。「専門の先生に見てもらいたいです」って、初診の時からすごい電話でアタックして。今もう9年から10年くらいお世話になっている先生がいるんですけど、その時に先生に会って「じゃあ、検査してみよっか」って検査したらADHDとLDという診断が下りました。
おとなLDラボ_Ten:
少し詳しく診断についてお聞きしたいのですが、あかねさんはどこで診断を受けたんですか?そこはどうやって見つけたのかと、覚えてる範囲で、どんな検査だったか教えてください。
あかねさん:
検査を受けたのは病院じゃなくて、大学の中の臨床心理センターみたいなところでした。主治医の先生からの紹介だったので、自分で見つけたわけではないんです。
ADHDの検査も受けましたが、LDの診断としては、算数の検査を受けました。そこで簡単にいうと算数や計算のテストをひたすらやる感じです。図形とかもありましたが計算が多くて数字ばっかり。時間も決められていて、すごく大変でしたね。
おとなLDラボ_Ten:
発達障害って診断を受ける前と後の気持ちの変化や周りの変化はありましたか?
あかねさん:
19歳の頃に夫と知り合っていて、ずっと相談をしてたんですよ。「すぐに気が散っちゃうし、忘れ物多いし、どうしよう」みたいな相談を、今の夫にしていたら、「もしかしたら発達障害があるんじゃない?」と言われて、そこで知ったんです。
そこから「じゃあ、診断に行ってみたら?」と言われたんですが、まずどこに行けばいいのか診断の仕方すらわかりませんでした。
病院に行って、検査が終わったらまず「算数障害をご存知ですか?」って心理師さんに言われたんです。全く知らなかったので、「なにそれ?」から始まって…そこからスタートという感じです。
本当に全く情報がなかったので、ADHDについては「原因がわかってよかった」と思ったんですが、LDの算数障害に関しては「え?それなんですか?」みたいなスタートでしたね。
もともと学習障害って読みと書きのイメージがすごくあったので、その中に算数があること自体、初耳だったんですよ。だから「算数障害とはなんぞや?」という、その驚きの方が大きかったです。
そこから25歳までずっと悩んでた時期に入ります。かなり長いです(笑)。「えっ?どういうこと?」みたいな混乱というか、自分の算数の困り事について自分の中に落とし込むまでかなり時間を要しました。
「それはあなたの強みだよ!」その一言で楽になった
あかねさん:
その頃はずっと接客業をやっていて、その時に、もう今は閉店してしまったサードプレイスカフェのマスターと出会いました。相談事ができるカフェみたいな感じで、気軽にマスターと話すことができるカフェで、その悩んでいた時期に相談したんです。「実は私、算数障害で、でも世間に言うのも悩んでて…。算数の数字の概念もあんまり分かってないですし、どうしたらいいですかね~情報も全然なくて…。」って。
そしたら、マスターが「できなくていい。それはあなたの強みじゃない?」って言ってくれたんです。「あかねさんは子どもが好きだから、あなたの経験を伝えることで子どもたちに勇気を与えられるんじゃない?」「自分のエピソードを話すことで、子どもたちは勇気づけられると思う。だから話してもいいんじゃない?隠さなくていいよ」っておっしゃってくださったんです。
それが本当にうれしくて、ずっと弱みだと思ってきて、隠さないとだめだと思ってきたから「いいんですか!?」みたいな(笑)
その時に、肩の荷が下りたというか、すごく楽になって。「じゃあ伝えていこう」「開示していいな」って思えるようになってSNSで「実は~」って自分のことを少しずつ言えるようになったんです。
おとなLDラボ_Ten:
すごく素敵なエピソードですね。そうやって外に向けて言えるようになって、周囲の反応などで印象的なことはありますか?
あかねさん:
同じ算数障害の当事者の方から「ありがとうございます!」って言われたり、「それわかります!」って共感していただいたりすることが多くて、本当にうれしいです。
一人じゃないんだっていう心強さがあって…ずっと一人で悩んできていたので、自分でなんとか試行錯誤して生きてきたからこそ、そうやっていろんな人の声が聴けるのはありがたいです。
あとは友達とかから「算数教えてあげる」って言ってもらえて、私は「じゃあ代わりに私ができることをやるね!」みたいな、いい意味での助け合いが生まれていて、そういう温かい助け合いの輪が出来ている気がします。
おとなLDラボ_Ten:
すごく良いですね。それはやはり自分の特性を公表しだしてから、自分の強みにも目を向けるようになったというかんじですか?
あかねさん:
いや、でも最初は全然できなかったので、ちょっとずつ段階を踏んで、本当に少しずつ進んできた感じになりますね。
アプリを駆使して数字と向き合う
おとなLDラボ_Ten;
あかねさんは、今現在、主婦として生活されているということですが、主婦ってやはり日常の中に数字があふれるお仕事だなと思うんですけど、日常の中での困りごととか、こういうツールを使っているという具体的な例はありますか?
あかねさん:
私は高校生の時からスマホを使ってきているので、とにかくアプリを使いまくっています。例えば、計算結果とかの数字が漢数字で下に表示されるアプリとか、消費税の計算をしてくれるアプリ、割引計算機で割引のパーセンテージを教えてくれるアプリ、どっちがお得ですよって教えてくれる価格の比較をしてくれるアプリとか、割り勘アプリ。とにかくたくさん入れて、試行錯誤しながら数字と向き合っています。
おとなLDラボ_Ten:
逆に、例えば人に頼るとか、ツール以外の部分で工夫していることはありますか?
あかねさん:
今、ありがたいことに周りに理数系の友達が結構多くて。理数系の子たちは手伝ってくれることが多いです。一緒にご飯を食べに行く時とかも全て友達に「ごめん!頼む」って言って計算とかお願いしてもらっています。
自分だけで買い物に行かなきゃいけないときは電話しながら計算してくれる友達もいます。電話しながら「どっちの方が安いかな?」って相談するときもあります。
おとなLDラボ_Ten:
友人同士での助け合いという面でもそうですけど、それはやっぱり根底にあかねさんの人間的魅力があるから、周りにそういう素晴らしい方も集まるのかなとお話を聞いていてすごく思いました。
今、お買い物の話がありましたけど、行政関係とか書類を記載する上での難しさもありますか?
あかねさん:
実は行政書類に関しては数字ってあんまり扱わないんですよ。たしかに書くことは多いと思います。役所とか行って書類で名前書いて必要なところを書いてくださいみたいなのは多いんですけど…唯一困るとすれば元号ですかね。
令和何年何月何日みたいなやつ。今も令和何年かわかんない。あとは保険証の番号を書かないといけない時とかも困りますね。そういった、数字の欄とかを書くときはすごい時間かかりますね。
おとなLDラボ_Ten:
ちなみにあかねさんは例えば見ながらだと書けるんですか?模写というか、見本があれば書ける?
あかねさん:
書けます。字は普通に書ける。わからないだけで全然文字に関してはそういう困難さもないですね。
おとなLDラボ_Ten:
なるほど。見本があれば書けるけど、それを暗記して思い出そうとした途端にパッと出ないみたいな感じなんですね。
今後、あかねさんが生活されていく中で将来的にこういうツールがあったらいいのになとか、ツールだけじゃなかったとしても、こういう配慮があったらいいなというものはありますか?
あかねさん:
まず算数障害がもっと広まるといいなというのが、一つあります。やはり、まだまだニッチな分野だと思いますし、わかる人はわかるけどわからない人は全くわからない、微妙な位置にあるものだと思っています。
「そういうのがあるんだなぁ」みたいな、なんとなくでいいので、もっと認知が広まってくれるとうれしいですね。そこから一緒にどんな対策ができるか、どんな配慮ができるか考えてくれるとより、良くなっていくと思います。
もう一つは、AIって実は算数が弱いんです。そこをちょっと強化してくれたらうれしいですね。あとは小学校とかに電卓使用を認めてほしいなと思います。タブレットとか、パソコンでもいいんですけど、自動で計算してくれるツールが導入されれば、子どもたちは自尊心を損なわないでいられるとおもうので。
おとなLDラボ_Ten:
今はすでに学校によっては算数障害の診断に関わらず、計算が苦手な子はツールを許可しているクラスもあるそうなので、もっともっと選択肢が増えるといいなと思いますね。
なかなか知られていない算数障害についてもっと広まってほしいという想いも、あかねさんがこうやって自身が表に出て顔出しもされて発信されているからこそ、すごく説得力のある言葉として響きました。
最後に、同じ悩みを持つ仲間に向けてのメッセージがあれば、ぜひお願いしたいです。
異世界転生してきたと思いながら、仲間たちとともに
あかねさん:
まず、すごく悩むと思います。「なんでできないんだろう?」がスタートで、できる(できない)理由がわからないし、まだまだ診断してくれるところも少ないですよね。
でも、算数ってどこにでも現れるじゃないですか。だから「自分は異世界転生してきた」って思いながら私は生きてるんですけど(笑)。
あとLDの交流会も最近開催されているので、いろんな当事者の方と話せて、私は見方が変わったりとか「自分だけじゃない」っていう気持ちがかなり強くなったから、悩みとかを一緒に話していけたらいいなと思います。
あとは「算数わかんないけど生きていけるよ!」みたいなプラス的な考えがちょっとだけでもあるといいなというのは結構思っています。
私の時代と今は、全然違っているなと思います。困ることもいっぱいあると思いますが、いろいろな情報がたくさんあるので、ぜひ調べてほしいですし、私も今後発信していきたいなと思っています。皆さんからも「こんなツール便利だよ!」という情報も、ぜひ教えていただきたいですね。
また、親御さんだけはお子さんの味方でいてあげてほしいと思います。算数がわからないからといって全部がダメなわけではないので、その子の長所を伸ばして、得意なところをほめてあげてほしいですね。
おとなLDラボ_Ten:
実際に交流会に参加されていかがでしたか?印象的な出来事はありましたか?
あかねさん:
私は進行(ファシリテーション)を行うこともあるので「大丈夫かな」と不安になることもあるんですが、終わった後にはすごく充実感があります。特に、「あるある話」というか、共感できるエピソードもたくさんあって、そういう話をできることがまず大きいですね。
あと、自分が伝える立場になったことで、しゃべり方や伝え方を日々考えながら生活するようになりました。
おとなLDラボ_Ten:
あかねさんありがとうございました!
本記事は、朝日新聞厚生文化事業団による「『発達障がい』とともに生きる豊かな地域生活応援助成2025」を受けて実施したインタビューをもとに作成しました。